|
|
|
12���̓ޗnj��c��ő�\��������܂����̂ł��v���܂��B
����21�N12��4��
 �����̍����O�̌o�Ϗ�Ԃ����܂��ƁA�~���E�h��������ϐi��ł���܂��B���̂܂܂ł͉䂪���̗A�o�Y�Ƃɑ傫�ȑŌ���^���A�f�t���ƂȂ��Ă��鍑���̌o�Ϗ������Ɉ���������̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜�����Ă���Ƃ��ł��B�{���ɂ����Ă��A���c��Ɍ��œ���69���~���z�����\�Z�Ă��o����Ă���܂��B�ޗnj��o�ς̏��A�S���Ɠ��l�ɑ�ό��������ɂ���Ɖ��߂ĒɊ��������Ă���킯�ł������܂��B�����ŁA�m���ɂ��q�˂������܂��B���ł̂����A�@�l�W�ł̗������݂����ɑ傫���킯�ł������܂����A�ǂ��������Ǝ�̌������傫���ł��傤���H�܂��A���N�x�̐Ŏ��͂ǂ̂悤�Ȍ��ʂ��ɂȂ�̂��H���������������B���{����₪�f�t���錾���o���A�ޗnj��o�ςɂ����Ă��i�C��ނɂ����v�̗������݂Ȃǂ���A�o�c�s�U�A�ٗp��̈����A�l����̗������݂ȂǁA��s���s���������}���ɋ��܂��Ă��܂��B���̂悤�Ȍ������̒��ŁA�o�ϊ�������ϋɓI�ɐ����i�߂�ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ƗU�v��z�e���̗U�v���܂߁A�����̊������ɂ��Ăǂ̂悤�Ȏ{���W�J��}���Ă�����̂��A�m���̏��������q�˂��܂����B �����̍����O�̌o�Ϗ�Ԃ����܂��ƁA�~���E�h��������ϐi��ł���܂��B���̂܂܂ł͉䂪���̗A�o�Y�Ƃɑ傫�ȑŌ���^���A�f�t���ƂȂ��Ă��鍑���̌o�Ϗ������Ɉ���������̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜�����Ă���Ƃ��ł��B�{���ɂ����Ă��A���c��Ɍ��œ���69���~���z�����\�Z�Ă��o����Ă���܂��B�ޗnj��o�ς̏��A�S���Ɠ��l�ɑ�ό��������ɂ���Ɖ��߂ĒɊ��������Ă���킯�ł������܂��B�����ŁA�m���ɂ��q�˂������܂��B���ł̂����A�@�l�W�ł̗������݂����ɑ傫���킯�ł������܂����A�ǂ��������Ǝ�̌������傫���ł��傤���H�܂��A���N�x�̐Ŏ��͂ǂ̂悤�Ȍ��ʂ��ɂȂ�̂��H���������������B���{����₪�f�t���錾���o���A�ޗnj��o�ςɂ����Ă��i�C��ނɂ����v�̗������݂Ȃǂ���A�o�c�s�U�A�ٗp��̈����A�l����̗������݂ȂǁA��s���s���������}���ɋ��܂��Ă��܂��B���̂悤�Ȍ������̒��ŁA�o�ϊ�������ϋɓI�ɐ����i�߂�ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ƗU�v��z�e���̗U�v���܂߁A�����̊������ɂ��Ăǂ̂悤�Ȏ{���W�J��}���Ă�����̂��A�m���̏��������q�˂��܂����B
�@����ɑ��Ēm�����A���N�x�̌��Ŏ����̓����\�Z�z�͐�S�l�\�~�ł������܂����B�\�����̒���z�A�ېŊz���猩��ƁA���Z���~�ŁA�O�N�x�̓������Ɣ�ׂĖE�O���A��\�ꉭ�~�̑啝�Ȍ��ƂȂ��Ă���܂��B���̒��ŁA�@�l�W�ł́A���E�I�ȋ��Z��@�ɂ�鐢�E�����s���̉e���������Ė@�l�̋Ɛт��}���ɗ�������ł��āA�@�l���Ɛł̒���z�͖��\�ꉭ�~�ŁA����A�����~�̌��ƂȂ��Ă���܂��B�������݂̑傫�ȋƎ�Ƃ��ẮA�{���̐Ŏ��ւ̃E�G�[�g�̍����@�B�E�������O�N�x��こ�̌��A�d�@����Z�ꁓ���ƁA���ɐ����Ƃ̗������݂��傫���Ȃ��Ă��܂��B���̑��̋Ǝ�ł��A�s���Y���Z�O�����A��s���l�������A�X�[�p�[�E�S�ݓX����ꁓ���ƁA�قڂ��ׂĂ̋Ǝ�ŁA�O�N�x��傫��������Ă���܂��B���N�x�̌��Ŏ����̌��ʂ��ł����A����̌o�ϓ����̐��ڂ�����܂��̂ŁA�����_�ł͕s�����ȂƂ��������܂����A���ɖ@�l�W�łɂ��ẮA�ŋ߂̉~���X���⊔���s���̒���A����ɂ͋Ɛт̈����ɔ��������z�𗂔N�x�ȍ~�ɌJ��z���@�l���������邱�Ƃ��l�����A�Ŏ��ɂƂ��Ă͌��O�v���������A���}�ȉ͍���ƌ��Ă���܂��B�{���Ŏ��̎l�����߂�l�����łɂ��Ă��A�������ٗp���l�����̒ቺ�̉e���ŁA����Ɍ������\�z����܂��B���̂悤�ɁA���ł���芪���Ŏ����͌������ɂ���A���N�x�̌��Ŏ����ɂ��ẮA�{�N�x�̐Ŏ��̓�����n�������v������ƂɁA���{�o�ό��ʂ��Ȃǂ̒��߂̊e��o�ώw�W��{���̌o�ϓ����A�@�l�̋Ɛї\�z�Ȃǂ𒍎����A���������݂̔c���ɓw�߂čs�������Ǝv���܂��B�Ƃ��܂����B
 �ޗnj��o�ς̊������ɓ������ẮA�U�v�ɂ��V���Ȋ�Ɨ��n�ƁA������Ƃ��o�����X�悭�A�Ƃ��Ɍo�ϔ��W�Ɍ����Ė������ʂ����ׂ����Â��肪�K�v���Ǝv���Ă���܂��B��Ɨ��n�̂��߂ɂ́A�s���̔M�S���Ɗ�Ƃ̃R�~�j�P�[�V�����̋������d�v�ȗv�f���ƐE���Ɍ����Ă���܂��B��2�N���̊ԂŁA�����g�̃g�b�v�Z�[���X���܂߁A���k�����͉��א��S����z���Ă���܂��B�{�N�̏���̗��n�����ɂ��ẮA�S���I�Ɏl�����̌����̒��A�{���͈�܁����̏\�ꌏ���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���������S���Ɣ�r���ĒႩ�����v���́A���O����̗��n�������������ʁA�����Œ����Ɍo�c����Ă����Ƃ��A����J�s��O�S�N�ՂɌ����������A�y�n�⌚�����i�̈�i�̉����܂����גn�ւ̓�����}��ꂽ���Ƃ��ƕ��͂��Ă��܂��B��Ƃ���芪�����͈ˑR�Ƃ��Č������A���{���Ƃ̗��n�����͂���Ɍ������Ă���ł������܂����A�����A�����Ŋ撣���Ă����Ƃւ̐ϋɓI�Ȏx�����̗v�ƔF�����Ă��܂��B���c�v�[���Ւn�̃z�e���U�v�ɂ��ẮA�ό��Y�Ƃ��䂪���̌o�ϊ������̂��߂ɏd�v�ȎY�Ƃł���܂�����A�d�v�Č��ƍl���A���������ʌ��^�̗U�v������W�J���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B���݂͓������͈ˑR�������A�c�O�Ȃ��猻�݂܂Ŗڗ����������������ł��B���������z�e�����j�Ƃ����܂��Â���\�z�̌����������Ƃ��܂����B �ޗnj��o�ς̊������ɓ������ẮA�U�v�ɂ��V���Ȋ�Ɨ��n�ƁA������Ƃ��o�����X�悭�A�Ƃ��Ɍo�ϔ��W�Ɍ����Ė������ʂ����ׂ����Â��肪�K�v���Ǝv���Ă���܂��B��Ɨ��n�̂��߂ɂ́A�s���̔M�S���Ɗ�Ƃ̃R�~�j�P�[�V�����̋������d�v�ȗv�f���ƐE���Ɍ����Ă���܂��B��2�N���̊ԂŁA�����g�̃g�b�v�Z�[���X���܂߁A���k�����͉��א��S����z���Ă���܂��B�{�N�̏���̗��n�����ɂ��ẮA�S���I�Ɏl�����̌����̒��A�{���͈�܁����̏\�ꌏ���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���������S���Ɣ�r���ĒႩ�����v���́A���O����̗��n�������������ʁA�����Œ����Ɍo�c����Ă����Ƃ��A����J�s��O�S�N�ՂɌ����������A�y�n�⌚�����i�̈�i�̉����܂����גn�ւ̓�����}��ꂽ���Ƃ��ƕ��͂��Ă��܂��B��Ƃ���芪�����͈ˑR�Ƃ��Č������A���{���Ƃ̗��n�����͂���Ɍ������Ă���ł������܂����A�����A�����Ŋ撣���Ă����Ƃւ̐ϋɓI�Ȏx�����̗v�ƔF�����Ă��܂��B���c�v�[���Ւn�̃z�e���U�v�ɂ��ẮA�ό��Y�Ƃ��䂪���̌o�ϊ������̂��߂ɏd�v�ȎY�Ƃł���܂�����A�d�v�Č��ƍl���A���������ʌ��^�̗U�v������W�J���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B���݂͓������͈ˑR�������A�c�O�Ȃ��猻�݂܂Ŗڗ����������������ł��B���������z�e�����j�Ƃ����܂��Â���\�z�̌����������Ƃ��܂����B
����ɑ��āA�ޗnj��̌o�ςɂ��āA���Ƃ��Ă����̐Ŏ��A���邢�͂܂��A���肵�����v���グ�Ă������߂ɁA��Ƃ̗U�v��A�z�e���̗U�v����������Ƃ���Ă������ƁA�m���͐���̒��Ōf���Ă����邪�A���̎���A�v���悤�ɂ����Ȃ��̂�����ł͂Ȃ����H��ƗU�v�ɂ��ẮA���S��Ƃ����Ƃ���փg�b�v�Z�[���X�܂ōs���ꂽ�Ƃ������Ƃ��悭���m�͂��Ă���܂����A����ς���т��オ��Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ����ʂƂ��ĔF�߂Ă����Ƃ����Ƃ���ɂ́A�قlj����ɂł͂Ȃ����H����w�A��ƗU�v�����Ŏ������グ���悤�Ȑl�𑽂��ٗp�ł���悤�Ȋ�ƁA�����������Ƃ���ɂ����L���撣���Ē��������Ǝv���܂��B
�@����ɑ��Ēm�����A�o�ς̊ϓ_�ł����q���g�������o���Ă��������Ă���܂����A���ɂƂ�܂��Ċ�Ɗ����̈Ӗ��ł����Ŏ����������܂����A�ٗp���厖���Ǝv���Ă���܂��B��ƗU�v�Ɋւ��ẮA�O����̊�ƗU�v�̑��A������Ƃ����C�ɂȂ��Ă��������̂��厖���Ǝv���Ă���܂��B�Ȃ��Ȃ��B��������ۑ�ł�����ƌ������͎������Ă���܂��B�p�������w�͂����čs�������Ǝv���Ă���܂��B�Ƃ��܂����B
 ����A23���܂ŊJ�Â���Ă��܂����������ł̂����Ō��鈢�C���ɂ́A��25��6000�l�A���ɑ����̑S���e�n���炨�z�����������A���ق��邽�߂ɒ��ւ̗ł��Ă���܂����B���N�J�Â���Ă��鐳�q�@�W���ߋ��ō��̖�30���l�̓��َ҂�����܂����B�ޗnj����ł͏t�H�̍s�y�V�[�Y���ɂ͍����O����̊ό��q�œ��킢�A���̎����ɓޗnj����֎Ԃł��z�����������ό��q�͂Ђǂ��a�Ɋ������܂�Ă��܂��B������x�Ɠޗǂɂ͗������Ȃ��Ǝv�������������Ǝv���܂��B�{���ł́A�a�؉�����}�邽�߂ɁA����24�����͂��ߍ���169�����A����308�����A����369�����Ȃǂɂ����Ă��A���H���ǂ�����_���ǂȂǏa�؉����̎{�u�����Ă��܂��B�m���͏�X�A�ޗnj����ւ̎Ԃ̏�������ɗ͗}�����������A����Ȑ�������Ƃ�ł������܂����A���̑�̈�Ƃ��āA�s���ւ̎Ԃ̏�������K������p�[�N�A���h���C�h�����{����Ă��܂��B�����������{�\���Ɍ��ʂ��グ�邽�߂ɂ͎Ԃł̗����҂̕��X�̒��ԏ�̖�������ʋK���Ɋւ������S���ɔ��M����ׂ��ł͂Ȃ����A�܂��A�ό��o�X�̒��ԏ�͓ޗnj������ӂł͔��ɏ��Ȃ��A�s���̏z�H�����������Ă���̂��a�̗v���ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�ȑO�ɂ��\���グ�܂������m�����ɁA���x�@�{�����ɂȂǂ��o�X��p�̒��ԏ�Ƃ��Đ�������Ă͂ǂ����H�m���̂��l�������������܂����B ����A23���܂ŊJ�Â���Ă��܂����������ł̂����Ō��鈢�C���ɂ́A��25��6000�l�A���ɑ����̑S���e�n���炨�z�����������A���ق��邽�߂ɒ��ւ̗ł��Ă���܂����B���N�J�Â���Ă��鐳�q�@�W���ߋ��ō��̖�30���l�̓��َ҂�����܂����B�ޗnj����ł͏t�H�̍s�y�V�[�Y���ɂ͍����O����̊ό��q�œ��킢�A���̎����ɓޗnj����֎Ԃł��z�����������ό��q�͂Ђǂ��a�Ɋ������܂�Ă��܂��B������x�Ɠޗǂɂ͗������Ȃ��Ǝv�������������Ǝv���܂��B�{���ł́A�a�؉�����}�邽�߂ɁA����24�����͂��ߍ���169�����A����308�����A����369�����Ȃǂɂ����Ă��A���H���ǂ�����_���ǂȂǏa�؉����̎{�u�����Ă��܂��B�m���͏�X�A�ޗnj����ւ̎Ԃ̏�������ɗ͗}�����������A����Ȑ�������Ƃ�ł������܂����A���̑�̈�Ƃ��āA�s���ւ̎Ԃ̏�������K������p�[�N�A���h���C�h�����{����Ă��܂��B�����������{�\���Ɍ��ʂ��グ�邽�߂ɂ͎Ԃł̗����҂̕��X�̒��ԏ�̖�������ʋK���Ɋւ������S���ɔ��M����ׂ��ł͂Ȃ����A�܂��A�ό��o�X�̒��ԏ�͓ޗnj������ӂł͔��ɏ��Ȃ��A�s���̏z�H�����������Ă���̂��a�̗v���ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�ȑO�ɂ��\���グ�܂������m�����ɁA���x�@�{�����ɂȂǂ��o�X��p�̒��ԏ�Ƃ��Đ�������Ă͂ǂ����H�m���̂��l�������������܂����B

����ɑ��čr��m�����A10��������11�����߂ɂ�����3���ԁA�}�C�J�[�̐i������Ȃǂɂ��ޗnj����̖��͌����ړI�Ƃ����Љ��������N�Ɉ����������{���܂����B�������A�啧�O�A�����܂ł̊e�����_�ɐݒu������������ᑐ�R�낭�̕��s�Ґ����啝�ɑ������Ă���A�ό��q����̕]���̔��ɂ悩�����ƕ]�����Ă��܂��B�p�[�N�A���h���C�h�ɂ͎s�����ƍ���23�����ˉ��ł̓s�[�N�Ŗ�500��̒��Ԃ�����A��ʍ��G�Ɍ��ʂ��������Ǝv���܂��B���N�͓��Ɋό��o�X�̗�������N�̖�2�{�ƂȂ茧�c��3���ԏ�ɂ��ď�p�ԂƊό��o�X�X�y�[�X�̊���U��ȂǁA��������啝�Ɍ��������Ƃɂ��A����ʍs��Ԃւ̊ό��o�X�̗����}����ɂȂ��������l���Ă���܂��B�Ƃ̂��l���ł���܂����B

�J�����ԋ߂ɂȂ��Ă܂���܂�������J�s1300�N�Ղɂ��Ă��f�����������܂��B����J�s1300�N�Ղ̒��ł�����ł��镽��{�Ղ�ɁA�����O���琔�����̂��q�l�����}�����Ď��{�����l�X�ȍs�Î��́A���{�ɂ�����ޗǂ̎��Ӗ��𐢊E�ɔ��M������_�@�ƂȂ�Ǝv���܂��B���̎����ɁA�����w�����͂��߂Ƃ���Ⴂ���オ����{�ՂɏW���A�𗬂����A���鋞�̎���������̂ѐU��Ԃ�Ȃ���A�����̐�����o�ς�A�����Đ������ǂ̂悤�ɍs���Ă����̂����w�сA�����b�Ƃ��������l���鎞�Ԃ������Ƃ́A���{�l�̏����ɂƂ��đ�ψӋ`�[�����Ƃł���Ǝv���܂��B�����͂��Ƃ��A���O����K��鏬���w�������{�̗��j�������y�����w�Ԃ��߂ɁA�ǂ̂悤�Ȏ��g�݂�i�߂Ă�����̂��m���ɂ��f���v���܂��B
����ɑ��Ēm�����A1300�N�Ղő�ɓa�Ȃǂ̕����{�݂���������镽��{�Ղɂ����āA���̃��[�����ɂȂ�܂����A�����O�A�C�O���瑽���̗��K�҂��}���鎖�ɂȂ�܂��B���{�̑b���z���ꂽ����Ɏv����y���A���j�Ɋw�Ԃ��Ƃ̂ł���悤�l�X�ȍs�Î���W�J����\��ł��B�{�Ղ����V���Ȃ���p�l���≹������ɂ�蓖���̏o�����Ȃǂ��w�ԓW�����͂��߁A�����w���ɂ����j�������y�����w�K���Ē������߂̑̊��̌����ł�����g�݂𐔑����v�悵�Ă��܂��B���鋞���j�قɂ����ẮA�����g�D�̕�����e�[�}�W���A�o�[�`�����f���ɂ�艝���̕��鋞�̗l�q�Ⓦ�A�W�A�𗬂̗��j���킩��₷���������\��ł��B�Q���̌��^�w�K�v���O�����Ƃ��Ă͏����w�����D��I�ɑ̌��ł���悤�A�C�w���s�A�Z�O�w�K���̒c�͕̂���{�Չ��ŃC�x���g���n�܂�O�ɐ�s���Ď�t���鎖�Ƃ��A���݁A�C�w���s�ɂ��Ă͊��Ɏ�t�������{���Ă��܂��B�Z�O�w�K�ɂ��Ă͋߂��U�v���i�̃p���t���b�g���쐬�A�z�z���A�w�Z�ւ̐�����ɂ��Ă����{����\��ł��B�Ƃ��܂����B
���ʐ^�Ō��銈���ցI
 �ޗǎs�ߍx�߂܂��ƁA�c�����i�̒��ɗ��j�I�Ȍ��������f���A�ޗǂ炵���i�ς��`�����Ă��܂��B���̌i�ς́A�_�Ƃ��c�܂�A�_�n���ۑS���邢�͊��p����Ă��邩�����Ă�����̂Ƒ����܂��B���݁A���암�ł͐���𒆐S�ɃC�`�S�A�g�}�g�A�����ăz�E�����\�E�A�V�����M�N�A�~�Y�i�Ȃǂ̖�ؐ��Y�A�ޗnj������R�Y�ł́A�����Y���s���A�ӗ~����S���肪�M�S�ɔ_�ƌo�c������Ă��܂��B�������Ȃ���A�����̔_�앨���i�̒����A�엿��R���Ȃǂ̌o�c�R�X�g�̑����ɂ����Ɍo�c�͋ꂵ���A���ɒ��̉ߏd�Ȓl����ɂ�蒃���Y�͋ꋫ�ɗ�������Ă���Ƃ�ł��B�����ŁA���݂̒��_�Ƃ̏ƁA���ꂩ��̒��_�Ƃւ̌��Ƃ��Ă̎��g�ނׂ��ۑ�ɂ��āA�m���ɂ��q�˂�v���܂��B�܂��A���͍���A����Ƃ��Đ\���グ�����̂́A11����{�ɒ��쌧�̂ق��ʼnʎ��_�Ƃ�K�˂܂����B���̒��ŁA���傤��6���c��ł��\���グ���Ǝv���܂����A�����S�_�����n�����g���ɂ���āA�Ⴆ�Εi��Ìy�Y���Ă����A���ɒn�����g���ɂ���āA���܂Œ��쌧�łƂ�Ă��������S�A�����Ď������O��Ă��̌�A�㔭�I�ɐX���Ń����S�Y����B11���ɂ͒���A12���A1���ɂ͐X�ƌ����`�ł���Ă����̂��A�n�����g���ɂ����n�K�����L�͈͂ɂȂ��Ă���܂��B �ޗǎs�ߍx�߂܂��ƁA�c�����i�̒��ɗ��j�I�Ȍ��������f���A�ޗǂ炵���i�ς��`�����Ă��܂��B���̌i�ς́A�_�Ƃ��c�܂�A�_�n���ۑS���邢�͊��p����Ă��邩�����Ă�����̂Ƒ����܂��B���݁A���암�ł͐���𒆐S�ɃC�`�S�A�g�}�g�A�����ăz�E�����\�E�A�V�����M�N�A�~�Y�i�Ȃǂ̖�ؐ��Y�A�ޗnj������R�Y�ł́A�����Y���s���A�ӗ~����S���肪�M�S�ɔ_�ƌo�c������Ă��܂��B�������Ȃ���A�����̔_�앨���i�̒����A�엿��R���Ȃǂ̌o�c�R�X�g�̑����ɂ����Ɍo�c�͋ꂵ���A���ɒ��̉ߏd�Ȓl����ɂ�蒃���Y�͋ꋫ�ɗ�������Ă���Ƃ�ł��B�����ŁA���݂̒��_�Ƃ̏ƁA���ꂩ��̒��_�Ƃւ̌��Ƃ��Ă̎��g�ނׂ��ۑ�ɂ��āA�m���ɂ��q�˂�v���܂��B�܂��A���͍���A����Ƃ��Đ\���グ�����̂́A11����{�ɒ��쌧�̂ق��ʼnʎ��_�Ƃ�K�˂܂����B���̒��ŁA���傤��6���c��ł��\���グ���Ǝv���܂����A�����S�_�����n�����g���ɂ���āA�Ⴆ�Εi��Ìy�Y���Ă����A���ɒn�����g���ɂ���āA���܂Œ��쌧�łƂ�Ă��������S�A�����Ď������O��Ă��̌�A�㔭�I�ɐX���Ń����S�Y����B11���ɂ͒���A12���A1���ɂ͐X�ƌ����`�ł���Ă����̂��A�n�����g���ɂ����n�K�����L�͈͂ɂȂ��Ă���܂��B
�����Ŕ_�Ƃ̕��X�͕i����ǂ�ϋɓI�ɐ����i�߂��A���쌧�ł͑����ɁA���������������S�̐V�i��ɂ���đ����o�����A�����o�ׂ����悤�ƌ������ŁA�����B�̗��v��Nj����Ă��������Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g����R�~���g���Ă̔̔��B�������g�̍���������S�����Ƃ��Ă����ڂ��q�l�֓͂������ƈꐶ�����ɂ���Ă����܂��B
�@�����������_�ƂƂ��Đ����c���Ă������߂̓w�͂ƌ����̂́A��X�A�撣���Ă��������Ă���킯�ł������܂����A�����ŁA�i�`�Ȃ炯��́A����11�N�Ɍ���̂i�`�ɂȂ�܂����B�����\�N���o�߂��������܂����B�i�`�ޗǎs�A�i�`�������ȂǁA�ޗnj����ɂ͍�����]�V�Ȃ����ꂽ�i�`����������܂��B�x�X�̓��p�����ǂ�ǂ�i��ł���܂��B�Ⴆ�A���ޗǎs�_���̊Ǔ��ł́A19�x�X��8�x�X���p�~����܂����B�����i�`�́A�_�Ƌ����g���@�Ƃ����@���ɂ̂��Ƃ��āA�_�Ƃׂ̈ɂi�`�͂���͂��ł��B�i�`�Ȃ炯��ɂ����ẮA�i�`�̂��߂ɔ_�Ƃ�����悤�ȏɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����H�����݁A���Z�Ƌ��ςɏd�_��u���߂��ł͂Ȃ��̂��H�����Ƃ����Ɖc�_�w���ɑS�͓��������Ă����������B�����ŁA�m���ɂ��f����v���܂��B���̂悤�Ȃi�`�Ȃ炯��ɑ��āA���Ƃ��Ă���܂ŐϋɓI�Ȏx��������Ƃ�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�i�`�ɑ��Ă̂���܂ł̎x��������������������B
 ����A�e���r�ŐV�����̒I�c�ł̔_�Ƃ̕ĂÂ��肪�Љ��Ă��܂����B��t������c��ڂɐ������߂Ă܂ŁA�D�ɏ���Ċ����肳���Ƃ���܂ŕ��f����Ă��܂����B����̓J�G��������Ƃ̋����ɂ���Ĕ_��͖��_��A��؍k���Ȃ��s�k�N�Ŗ��엿�ł̕ĂÂ�����������Ă���܂����B���̕Ă����ƁB�����̕S�ݓX�Ŋ��i�̕ĂƂ��Ĉ�\��\���~�قǂŔ����A��ςɋ����������܂����B�܂��A������̃n�[�u�����钆�ŁA�C�M���X�ł����炽�Ȃ��n�[�u���͔|����_�Ƃ͈ꈬ��ł͂���܂����A���\���~���牽�S���~�Ƃ����P�ʂŔ����Ă��܂��B��قǐ\���グ�܂������쌧�̉ʎ��_�Ƃ̎�����l�����킹�܂��ƁA�i����ǂɂ��V�����_�앨�̐��Y�A���F�̂��鐶�Y�Z�p�̓����ȂǁA�o�c�̂�肩������ł͂��ꂩ��̔_�Ƃɂ�������҂����Ă�̂ł͂Ȃ����A���̂悤�ɍl���܂��B�����ō����̌������_�ƌo�c�����P�����肵��������������o�c����������ׂɂ́A�s�s�ߍx�Ƃ����ޗnj��_�Ƃ̓��F�������{���W�J���K�v�ł���ƍl���܂��B�����ŁA���_�Ƒ����Z���^�[�̂���܂ł̎��g�݂�ʂ⍡��̌��������ɂ��āA�_�ѕ����ɂ��q�˒v���܂��B ����A�e���r�ŐV�����̒I�c�ł̔_�Ƃ̕ĂÂ��肪�Љ��Ă��܂����B��t������c��ڂɐ������߂Ă܂ŁA�D�ɏ���Ċ����肳���Ƃ���܂ŕ��f����Ă��܂����B����̓J�G��������Ƃ̋����ɂ���Ĕ_��͖��_��A��؍k���Ȃ��s�k�N�Ŗ��엿�ł̕ĂÂ�����������Ă���܂����B���̕Ă����ƁB�����̕S�ݓX�Ŋ��i�̕ĂƂ��Ĉ�\��\���~�قǂŔ����A��ςɋ����������܂����B�܂��A������̃n�[�u�����钆�ŁA�C�M���X�ł����炽�Ȃ��n�[�u���͔|����_�Ƃ͈ꈬ��ł͂���܂����A���\���~���牽�S���~�Ƃ����P�ʂŔ����Ă��܂��B��قǐ\���グ�܂������쌧�̉ʎ��_�Ƃ̎�����l�����킹�܂��ƁA�i����ǂɂ��V�����_�앨�̐��Y�A���F�̂��鐶�Y�Z�p�̓����ȂǁA�o�c�̂�肩������ł͂��ꂩ��̔_�Ƃɂ�������҂����Ă�̂ł͂Ȃ����A���̂悤�ɍl���܂��B�����ō����̌������_�ƌo�c�����P�����肵��������������o�c����������ׂɂ́A�s�s�ߍx�Ƃ����ޗnj��_�Ƃ̓��F�������{���W�J���K�v�ł���ƍl���܂��B�����ŁA���_�Ƒ����Z���^�[�̂���܂ł̎��g�݂�ʂ⍡��̌��������ɂ��āA�_�ѕ����ɂ��q�˒v���܂��B
�@����ɑ��āA�m�����A�����ɂ��܂��ẮA���l�Ȉ��������y���A�}�{�ň��ރ��[�t���̏������ɉ����āA����16�N�̂����̃y�b�g�{�g���u�[���ȍ~�A���Y�ߏ�A���ʍɉߏ�Ȃǂ������A���Y�Ҕ̔����i��������Ă��܂��B����A�엿�A�R���̍��������琶�Y�R�X�g�����~�܂肵�A�S���I�ɔN�X���_�Ƃ̌o�c���ꂵ���Ȃ��Ă��܂��B�{�N�͐Ԏ��o�c�ɂȂ����_�Ƃ�����Ǝv���܂��B����������ŊJ����ɂ́A���i���ȑ�a���̐��Y�͂������̂��ƁA���������Ƃ����C���[�W�Â���A����g��͂ǁA�}�[�P�b�g�헪�Ɋ�Â����s�f�̓w�͂��s�����ƔF�����Ă��܂��B����܂ł̌��̓w�͂ł����A���c�����_�n�J�����Ɠ��ɂ�鉀�n�����A�����đ�^�����r�����H�{�݂�L�撃���ʃZ���^�[�̐����A��p�^�E�̋@�̓����Ȃǂ����Ă��܂��B�����Y�����L���ɂ��g���[�T�r���e�B�[�ւ̑Ή������Ă��܂��B�܂��A�̔��̂ق��ł����A�������̍����z�e�����͂��߁A��a���J�t�F�Ƃ����悤�ȃC�x���g�A�ޗǃt�[�h�t�F�X�e�B�o���Ȃǂł̍�����a���̒����Ă���܂��B����ɏ��i�J���ւ̎x����e��C�x���g�ł̎����B�����ɂ���a���̏���g��ȂǁA���Y�A���ʁA�̔��Ɏ���e�ʂ̎��g�݂��x������W�J�����Ă��܂��B����́A���ɘV�ؒ����̎�Ԃ��}��ۑ肪����܂��B���̉��A���Ƃ�ϋɓI�ɐ��i����ƂƂ��ɍr�����H�@�B�̍X�V�x�����ƕ����āA��w�̍��i�����Y�U����}��܂��B����J�s1300�N�Պ֘A���ƂƂ��đS�������܂��{���ŊJ�Â���ׂ��A�W�c�̂Ə�����i�߂Ă��܂��B��a���u�����h�̎��m��}��Β��S�̂̏���g��ɓw�߂Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B�i�`�Ȃ炯��ɂ����ẮA�͔|�Z�p��y��f�f�Ȃǂ̉c�_�w���A�_�Y���̈ϑ��̔��A�엿��_��Ȃǂ̍w���Ȃǂ̌o�ώ��ƂƌĂ�Ă�����̂̂ق��A�M�p���ƁA���ώ��ƂȂǂ̎��Ƃ�����Ă��܂��B���ɂ��i�`�ւ̎x���Ƃ��ẮA�c�_�w���̋������d�v�ł��邱�Ƃ��猧�_�Ƒ�w�ɂ����Ăi�`�E����Ώۂɉc�_�w�����̗{�����C�����s���Ă��܂����B�ߋ��ɂ́A�_�Ǝҕی��ړI�Ɍo�c����_���̍�����A�s�Ǎ��̏�����o�c�̍�������}�錧�P��_�������{���邽�߂Ɍo�c��Ո���̂��߂̍����I�x�������{�Ă����o�܂�����܂��B���̓����̋�̓I�Ȏx�����@�́A�����疳���q������݂��t���A���̉^�p�v�łi�`�����Ƃ��s���Ƃ������̂ł����B�o�c�̈�����������݂ł́A�݂��t���͎��{���Ă���܂���B�܂��A�_�Ƃ̒S����m�ۂƔ_�n�̂�������Ȃǂ��T�|�[�g����S����o���N�V�X�e���^�c�ȂǂɁA�ߋ��ܔN�ԂŖ��疜�~��⏕���Ă���܂��B�i�`�̌o�ώ��Ƃ̏[���́A���̔_�Ƃ̔��W�̂��߂ɕK�v�ł������܂��̂ŁA�[�������҂��Ă��܂��B
�@�ޗǂɂ��܂����̂Ȃ��A�Ƃ����]���@���邽�߁A���Y�H�ނ��g�����ޗǂ̂��������H�̑n���Ɏ��g��ł���܂����A�i�`�����̂悤�ȕ����ł̊������������Ă�����������Ǝv���܂��B�܂��A�̘H�̊g�傪�d�v���ƍl���܂��B���Ƌ��蒼������ݒu���ăh���C�u���ł̘̔H�̊g����x�����Ă���܂����A����A��^�������⒭�]�̂悢���X�g�����̐ݒu���Ɍ����āA�i�`�Ȃ炯��Ƃ��A�g���͂��Ď��g��ł��������Ǝv���܂��Ƃ̂��ӌ��ł����B
�@�܂��A�_�ѕ����́A���_�Ƒ����Z���^�[�ł́A�n��̓y�n������C�ۏ����Ȃǂ̓������͂��ߔ_�Ǝ҂̐��Ȃǂ܂��Ȃ���A��ɂ́A�t�����l�̍������͂�����Y���̊J���A�܂��A�J�����S�̌y���̂��߂̏ȗ����A�y��Ɖ��Z�p�̊J���A����ɂ́A���ۑS�^�_�ƂɎ����鎝�����̍������Y�Z�p�������ڕW�Ƃ��Ē�߁A�Y�ƊE�A�����@�ցA��w���Ƃ̎Y���w�A�g���ďd�_���������{���Ă��܂��B�C�`�S�̃A�X�J���r�[��n�E�X�`�A���n�z�E�����\�E�Ȃǂ̓��Y���̊J���B�`�̑�ʒE�a���@�A�C�`�S�̍��ݍ͔|�Z�p�A�V�N�������Ȃǂ̔��y�̊J���ɂ��ȗ����A�y��Ɖ��A����ɂ́A���z�M���p�ɂ��n�E�X���̓y����Ŗ@�A�܂����R�Ԓn��̏b�Q��Ƃ��ĊȈՃl�b�g�����N�Ȃǂ̊J�����s���A���̎��X�̔_�ƐU���Ɋ�^���Ă��܂��B���݁A�C�`�S�̐V�i��Ós��A���i����a�}�i�A�킫��̏o�Ȃ��e�Ȃǂ̈琬�A3�N�Ŋ`�𐬂点���c�Z�p�̊J���A�E�C���X�ɐN����Ă��Ȃ��_���A�����̐��Y�Z�p�ȂǁA���p���̂߂ǂ̂���������������n�߂Ă��܂��B����Ƃ��A�}�[�P�e�B���O�헪�Ɋ�Â��Đ��ʂ����A���y�Ɍ�������Ɖ��𒅎��ɐ}���Ă܂���܂��B�Ƃ��܂����B
 �����ޗǕa�@�̌��ւ��ɍۂ��ẮA�ꍏ���������x��Ë��_�Ƃ��Đ��������Ē��������A����Ȏv��������w����Ă���킯�ł������܂����A���N�x�̗\�Z�Ґ��Ɍ����ċ�̓I�ɂǂ̂悤�Ɏ��g��ł���̂��H�m���̏��������f���������܂��B�܂��A���~�n���̋~���~�}�Z���^�[�ɂ͖��҂⎩�E�����҂���������A���̏�A����a�ł��������܂����a�Ȃǂ̐��_�����������Ƃ����ӂ��ɕ����Ă���ł������܂��B���̍ہA�����ޗǕa�@���ɑ����ɐ��_�Ȃ̊J�݂��K�v�ƍl���܂����A���킹�Ă����������B�܂��A�m������9���c��ɂ����Č�����ȑ�w�ړ]����������܂����B���݂̌�����ȑ�w�̏�����A�����a�@�̐����[���̂��߂ɋ��畔��̈ړ]���̂��̂̕K�v���́A�����g�͎^��������̂ł���܂��B�ړ]��ɂ��ẮA���L����������Ƃ����悤�ȓ��قł��������܂����B�n�������͂��ߒ���a�n��̐��̐�����������ƕ�����A���g��Œ��������Ǝv���܂��B���̂��Ƃɂ��Ă͈ӌ���t���ċ������v�]��\���グ�܂��B�����Ă܂��A�n���ÍĐ��v��ł́A�ꎟ�~�}�ɂ��Č������ɋ��_���[��������Ƃ���Ă��܂��B����̎��g�݂͂ǂ̂悤�ɐi�߂悤�Ƃ���Ă���̂��H�m���ɂ��l�������q�˂������܂��B �����ޗǕa�@�̌��ւ��ɍۂ��ẮA�ꍏ���������x��Ë��_�Ƃ��Đ��������Ē��������A����Ȏv��������w����Ă���킯�ł������܂����A���N�x�̗\�Z�Ґ��Ɍ����ċ�̓I�ɂǂ̂悤�Ɏ��g��ł���̂��H�m���̏��������f���������܂��B�܂��A���~�n���̋~���~�}�Z���^�[�ɂ͖��҂⎩�E�����҂���������A���̏�A����a�ł��������܂����a�Ȃǂ̐��_�����������Ƃ����ӂ��ɕ����Ă���ł������܂��B���̍ہA�����ޗǕa�@���ɑ����ɐ��_�Ȃ̊J�݂��K�v�ƍl���܂����A���킹�Ă����������B�܂��A�m������9���c��ɂ����Č�����ȑ�w�ړ]����������܂����B���݂̌�����ȑ�w�̏�����A�����a�@�̐����[���̂��߂ɋ��畔��̈ړ]���̂��̂̕K�v���́A�����g�͎^��������̂ł���܂��B�ړ]��ɂ��ẮA���L����������Ƃ����悤�ȓ��قł��������܂����B�n�������͂��ߒ���a�n��̐��̐�����������ƕ�����A���g��Œ��������Ǝv���܂��B���̂��Ƃɂ��Ă͈ӌ���t���ċ������v�]��\���グ�܂��B�����Ă܂��A�n���ÍĐ��v��ł́A�ꎟ�~�}�ɂ��Č������ɋ��_���[��������Ƃ���Ă��܂��B����̎��g�݂͂ǂ̂悤�ɐi�߂悤�Ƃ���Ă���̂��H�m���ɂ��l�������q�˂������܂��B
����ɑ����A�k�a�n��̍��x��Ë��_�a�@�Ƃ��ĘV�������i��ł��錧���ޗǕa�@�ɂ��āA�����������̒��ł͂���܂����A�傫�ȓ������s�����ӂ������đS�ʓI�Ɍ��đւ���K�v������ƍl���Ă��܂��B���݁A�����Ƀv���W�F�N�g�`�[����ݒu���āA�a�@�̋@�\�A�����ȂNJ�{�I�R���Z�v�g��a�@�S�̂̋K�́A��܂��Ȏ��Ɣ�Ȃǂ̎��ƊT�v����X�P�W���[���̌������n�߂Ă���܂��B���̒��ŁA���ݒn�Ō��đւ����ꍇ�̐f�Âւ̉e����A�ړ]�����ꍇ�ɂǂ̂悤�ȉۑ肪���邩�Ȃǂɂ��Ă��o�����s���Ă���Ƃ���ł��B���N�x�\�Z�ɂǂ̂悤�ɔ��f���邩�A�}�����ꂩ��̌�����i�߂Ă܂���܂��B
�@�܂��A���w�E���܂������E�����҂Ȃǂŋ~���~�}�Z���^�[�֔��������~�}���҂ւ̑Ή��Ȃǐ��_�����ւ̐f�Ë@�\�̋����ɂ��ẮA��{�I�ȃR���Z�v�g�̍���̒��Ō������Ă܂���܂��B���݂̓ޗnj��̈�Â̎���̒��ŁA��O���̋~�}�����a�@�������̌y�NJ��҂�����邱�ƂŁA�d�NJ��҂�������Ȃ��Ƃ����������Ă��܂��B�y�NJ��҂�I�m�ɎƂ߂�ꎟ�f�Ñ̐��̏[�����K�v�ł��B�x����ԉ��}�f�Ï��́A�s�������ƂƂ��Ă��ꂼ��̒n��ʼn^�c����Ă��܂��B�����̒n��Ŗ�Ԃ̐f�Ñ̐����������ɂȂ��Ă���܂��B�܂��A�����ݔ����\���łȂ����Ƃ�A���v�̑��������Ȃ̐��オ�z�u�ł��Ȃ����ƂȂǂ̉ۑ肪�������܂��B�����S��̎s�����ɌĂт����A�s�����s��������c�ɍ�ƕ����ݒu���A����11���Ɉ��ڂ̈ӌ��������s���܂����B�n���ÍĐ��v��ł́A��̏[������Ƃ��ċ��_�ƂȂ�x����ԉ��}�f�Ï��̐�������܂������A����͎s�����Ƃ̃��[�L���O�O���[�v��ݒu���āA���̈ӌ��������Ȃ���A�������s���Ă܂���܂��B
�@���ɁA�~�}�̐��ɂ��ẮA�܂��́A�W���鎩���̂�a�@���A���ꂼ��̕a�@�̈�Ë@�\�ɂ��ď\���������邱�Ƃ��K�v�Ȓi�K�ł��B���Ƃ��ẮA�f��Ȃ��~�}�@�\�������x��Ë��_�a�@�����邱�ƂŁA�n��̕a�@�ŏd�lj��������҂��m���ɎƂ߂�V�X�e�����\�z���鎖���d�v�ƍl���Ă���܂��B�ƎO���̘A�g���s���邱�ƂŁA�̐��̏[���ɂȂ�����̂ƍl���Ă���܂��B�Ƃ̂��l���ł����B
|
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
| 6���c��ł̑�\���� |
|
|
| ����Ɨ��n�E�U�v�ɂ��� |
|
�r��m�����A�C�ȗ��A��ƗU�v�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��邱�Ƃ�]�����Ȃ�����A�����Ƃ̋��������������Ŋ�ƂɂƂ��Ė��͓I�ȗ��n���Ȃ��ƁA�U�v�͓���ƍl���A�H��p�n�m�ۂ̂��߂̍H�ƌn�p�r�n���O��Ƃ����s�X�����ւ̕ғ���ϋɓI�ɐ��i���鎖�����߂܂����B�܂��A����܂ł̉c�Ɗ������Ƃ̔����y�ь���ɂ��Ă̐��������߂��Ƃ���ł��B
�@����ɑ��čr��m���́A�o�ϊ������̂��߃C���^�[�`�F���W���ӂ̍H��E���ʋƖ��ɓK����y�n���s�X�����ɕғ�����Ȃǂ��čH�Ɨp�n�g��ɓw�߂�Ƃ��܂����B��Ɨ��n���������邽�߂ɂ́A�s���̔M�S���Ɗ�ƂƂ̃R�~�j�P�[�V�����������d�v�ȗv�f�ł���Ƃ̔F���ŁA�����r�b�O�T�C�g�ŊJ�Â��ꂽ�u���ۑ��z�d�r�W�v��C���e�b�N�X���ŊJ���ꂽ�u������Ƒ����W�v�Ȃǂɏo�X������ƂƂ̖ʒk��ϋɓI�Ɏ��{���A�ޗnj��̖��͂�x�����x��PR�������ʁA����܂ł̓�N�ԂŊ�ƂƂ̑��k�����͐���A52���̗��n������܂����B���̂���18���͏��߂ēޗnj��ɐi�o������Ƃł��B����Ƃ��ٗp������m�ۂɂȂ���D�NJ�Ƃ̗��n��ϋɓI�ɐi�߂�Ƃ��܂����B |

�����㓹�H�S�R�C���^�[�`�F���W�t�߁B |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
| ���z�e���̗U�v�ɂ��� |
|
|
|
�ޗnj��c�v�[����p�~�E�P�������Ւn�Ƀz�e����U�v������j�Ős�͂��Ă��܂����A�����̖ڏ����������A�אڂ���ޗnjx�@���̈ړ]�v��ɂ��U�v�����𐮂����Ƃ��Ă��A���̌o�Ϗ�ł̓z�e���U�v���������邱�Ƃ͓���ɂȂ��Ă��܂��B�r��m���������z�e����U�v���悤�Ƃ��Ă���̂��H����ɁA���ԃ��x���ł̃z�e�����n�ɂǂ��ւ���Ă����̂������₵�܂����B
�@�r��m���́A���������ʌ��^�̗U�v������W�J���Ă�����̂́A�ڗ����������͂Ȃ��Ɠ��ق��܂����B�܂��A���Ԃɂ��h���{�݂̗��n����ɑ��ẮA�ݔ������ւ̗Z�����x��o�c�A�h�o�C�X�A���ł̓���ɂ�鎖�Ɛŋy�сA�s���Y�擾�ł̌y�����u�A���n���Ɋւ�����A���Ǝ҂ƒn��E�s�����ւ̃}�b�`���O�T�|�[�g�Ȃǂ̎x���Ɏ��g��ł����Ƃ��܂����B |

���c�v�[���Ւn�ւ̃z�e���U�v�́H |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
| ���ޗnjx�@���̈ړ]���I |
|
|
|
�z�e���̗U�v�Ɋ֘A���ėאڂ̓ޗnjx�@���ړ]��肪���サ�Ă��܂��B�ޗnj��͈ړ]��Ƃ��ēޗnj��_����ٓ�ׂ̓ޗnj��������ɂ��������Ă��܂����A�����͏o����������ʍs�K���ŗ����ɗ��Ǝv���܂��B
�@�ޗnj��x�@���͏\�N�O�ɎO�����疜�~�Ń��j���[�A����������ŁA�ޗnj����ł͐���̂悤�ɋً}�Ɏ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�@�������ɂ���܂��B�x�@���������ւ̑f�����Ή��͂�ً}�������߂��邱�Ƃ��l����A�ړ]��Ƃ��Ă͍��̓ޗǏ���藧�n�����ŗ��Ǝw�E���A�m���̔��f�����߂܂����B
�@�r��m���́A�ޗnjx�@�����z��l�\�N���o�߂��A�ϐk�����Ȃ����Ƃ��猚�đւ�����K�v������A���~�n���ł͋Ɩ��ւ̎x��◈���҂̕s�ւ��\�z����A�ޗnj��������ɕ~�n�ւ̈ړ]���l���Ă���Ƃ��܂����B�����ɂ�JR�ޗljw�ɂ��߂��ߗׂ̓��H�g�������ɂ�荡�㓹�H�A�N�Z�X�����シ�錩�ʂ��ł���A���݂̓ޗnjx�@���Ɠ����̋@�����m�ۂ��\�ł���A�ړ]��Ƃ��ēK�n�ł���Ƃ��܂����B
���ʐ^�Ō��銈���ցI |

���c�v�[���ɗאڂ���ޗnjx�@�� |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
| ����Â��x����l�ނ̈琬 |
|
|
|
�@�M�������~���Ȃ��������Ⴊ�������A��Ñ̐��̏[���Ɏ��g��ł��܂����A���̖��̕���21�N3���A����s�ŋ~�}���҂̂��炢���N���Ă��܂��܂����B���̂��Ƃ�����~�}��Â̗l�X�ȉۑ肪��������Ă��܂���B���̌����Ƃ��đ����̋~�}�a�@�ň�t����l�œ��������Ă���ȂǓ����̐����Ǝ�Ȃ��ƁA�Ζ����Ԃ��������ƂȂNj~�}��Ì���̋Ζ������ߍ��ł��邱�Ƃ��w�E���܂����B�܂��A�~�}��Ñ̐��ɐϋɓI�ȗ�Ƃ��ĉ��ꌧ�������a�@�̎��g�݂��Љ�܂����B���a�@�͕a����550����L���A�y�ǂ���d�ǂ܂ł̊��҂������ER�����i1���`3���܂ł̋~�}���҂���ʂȂ�����A24����365�������x���̈�Ð������ێ����邽�ߋ~�}�ꑮ���z�u�j�̋~���~�}�Z���^�[���^�c���Ă���A�S�����瑽���̎���t���W�܂��Ă��܂��B���ꌧ�̎��g�݂��Љ�Ȃ���A�Ⴂ��t��{�����邽�߂̎{��ɂ��Č��̎p���������܂����B
�@�������N���S�ǒ��́A�Ⴂ��t���������{�����邽�߂ɁA�ޗnj��Տ����C�A�����c��i���́j��ݒu���A��w�������̗Տ����C�a�@�̍����������Տ����C���M����|�[�^���T�C�g�̊J�݁A���C������v���O�����̏[���A�������P�������{���Ȃ���A�S�����猤�C������ق������Ƃ��܂����B |

�����ޗǕa�@�Ƃ̘A�g���s���Ǝw�E���ꂽ
�~���~�}�Z���^�[�i����͓ޗǕa�@�j�B |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
| ���_�n���ɂ��āI |
|
|
|
�@�_�Ɩ��ɂ��ẮA����3�_�ɂ��Ď�������܂����B
�@���ޗnj��ɂ�����k������n��2010�w�N�^�[���ɋy�ё傫�Ȗ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���̉����̂��߂ɂ͍��̔_�n�E���E
�@�@�@���ۑS����Ƃ͗L���ȑ�Ǝv������̂́A�����Ƃ͕���23�N�܂łł���A24�N�x�ȍ~���p�������悤
�@�@�@���֗v�]���ׂ��ł��邱�ƁB
�@���_�Ƃ̒S�����ɂ́A���͂���_�ƌo�c�ƂƂ��Ɉ��肵�����v�鎖���ł��邩�Ŏ�҂̏A�_���\�ɂȂ�Ǝv���
�@�@�@�܂����A���̓_�ɂ��Ăǂ̂悤�ȑ���u���ė���ꂽ�̂��B
�@��JA�ޗnj����g�D��������10�N���o�߂��܂������A���̊ԁA�x�X�̓��p���⋤�ρA���Z�ɏd�_���u����A�̔���c�_�A�_��
�@�@�@�w���ւ̓w�͂��Ȃ���ė��Ȃ������Ǝv���܂��B���������_�ɗ����Ԃ�A�n�Y�r����}��V�N�Ȕ_�앨��̔������^
�@�@�@��������ݒu���ׂ��ł͂Ȃ����B
�@�@����ɑ��Đ��_�ѕ����́A���̔_�n�E���E���ۑS����Ƃɂ��āA���̗v�]�����֓`����Ƃ�����ŁA�S����
�@�@�@��Ƃ��Ď��v�����Ɣ�p�팸��}�邽�ߐ��Y�E�̔��E�o�c�ʂł̎x���Ƃ��āA���t�����l���ւ̎��g�݁A��s���ł�
�@�@�@�̔����i�A�_�Y���Y�������ւ̎x���A���x�����̊��p�A�o�c�y�і@�l���ւ̎w���Ȃǂ����{���A�l�ނ��m�ۂ��邽�ߔ_��
�@�@�@��w�Z��2�N����1�N�ɉ��҂���ȂǓI�m�Ō����I�Ȏx���Ԑ��𐮂���Ƃ��܂����B
�@�@�_�Y���������́A���E�s�����EJA�E���Y�g���Ȃǂʼn^�c������̂�110��������܂��B�����͒n�Y�n���̐��i�A�n��_�Ƃ�
�@�@�@�������ɏd�v�ƍl���A19�����̒������Ƌ������肵�u�n�̖��A�y�̍��v�u�����h�̊m�����߂����A��^�̔_�ƕ��������̐ݒu
�@�@�@�������������Ƃ��܂����B |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
| �����H���ɂ��� |
|
|
|
�@��a�������͓�k���т�����H�ł���ƂƂ��ɁA��a�S�R�s���ł͐����㎩���ԓ��ɃX�}�[�g�C���^�[�`�F���W�̐������\�肳��Ă��܂��B�܂��A�ޗǎs�Z�̖�������Ԃł́A�ǍD�ȏZ��n����ׂ��p�n���擾����Ă��܂����A���Ƃ��đ�a�������̖�������Ԃ��ǂ̂悤�ɂ����̂��A�܂��A�Z����Ђ����L����p�n�̊��p�@�ɂ��Ď�������܂����B����ɁA����308����{�ʂ�̍�ޓ��H�����H��ō��ˉ����i�߂��Ă���4��27������ꕔ�̋��p���J�n����܂����B�����A�n���ւ̐����ł͍��˂������ޗL�����H�ڑ��ł���Ƃ��Ă��܂������A�����ɂ͐i�����鎖���o���܂���B���̍��˂𗘗p���đ����ʂ��痈��ꂽ�ꍇ�A�O��A���̐M�������邱�ƂŋߓS���������z�����n�_����a����������̂ł͂Ɗ뜜���Ă���A�r��m���̏����������܂����B
�@�r��m���́A��a�������͊������H�Ƃ��Čv�悳��܂������A���̐����𑖂閇����a�S�R����4�Ԑ��̊���H�Ƃ��Đ�������A�����̍��K�i�������H�̑�a�k���H�����Ɖ������ȂǁA��a����������芪�����́A�s�s�v�挈�肳�ꂽ25�N�O����傫���ω����Ă���A����ɂ͑S���I�Ɍ�ʗʂ��������Ă�����Q�l�ɂ��Ȃ���A���̕K�v���ɂ��Č����������Ƃ��܂����B��a�������֘A�̏Z������Зp�n�ɂ��ẮA�o�Ϗ�l�������ɂ��Z��y�яZ��p�n�̎��v���Ԃ�̎Z�������ɂ߂Ȃ��画�f�������Ƃ��܂����B��{���H�Ƒ���ޗL�����H�Ƃ̐ڑ��ɂ��ẮA��{���H�̍��˕��������ރ����v�ւ̒��ڏ����ꂪ�\�ƍl���Ă��܂������A��s�������H�ɂ����铯�l�̕��������ɂ����Ď��̂��������Ă��邱�Ƃ���A���S�����ŗD�悵���ڏ�����𐧌����܂������A������P�Ɍ����Z���̊F�����x�@�Ƒ��k���Ȃ�����g�ނƂ��܂����B��{���H�����̘A������M���@���a�̌����ɂȂ�̂łƂ̎w�E�ɂ��ĘA����������ƕ��s����O�H��4�Ԑ��Ɋg�����邱�Ƃʼn����������̂Ƃ��܂����B |

���˂������ޗL�����H�ɐi���o���Ȃ�
R308�������H��B |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
|
|
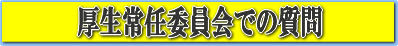 |
|
|
|
�@���c�c���́A���݁A������C�ψ���y�ъ����E��ʑ����ʈψ���ɏ������Ă��܂��B���ꂼ��̈ψ���ł́A����������ۑ����_�ɂ��ċc���������ґ��Ƌ�̓I�ȋc�_�����킵�Ȃ���A�ޗnj��������S�Ɉ��S���ĕ�点��n��Â�����߂����Ă��܂��B
8��5����9��11���ɊJ�Â��ꂽ�����ψ���ŗ����҂Ƃ̊ԂŎ��̂悤�Ȏ��^����������܂����B
���ޗnj��ŊJ�Â���Ă��鍂�Z���̂ŁA�I�肽�����V�^�C���t���G���U�Ɋ�������ȂǑ�ςȒ��ŁA���A�ǂ̂悤�ȏ�
�@�@�Ȃ��Ă���̂��A����ɓ~��O�ɂ��Ă̑Ή��ɂ��Ď�������܂����B
�@�@�S���҂́A�Ή���Ƃ��Ĕ��M���k�Z���^�[��ݒu�������h�~�ɓw�߁A�\�h��̔��~��i�߂Ă��܂������A����͊������
�@�@�d�lj��A���ǁA���S����������ɂȂ������ɏd�_��u������Ñ̐��̐������s�������Ƃ��܂����B |
���ޗnj����a�@�͘V�������������A�t���̋~���~�}�Z���^�[�Ƃ̘A�g
�@�@���X���[�Y�ł͂Ȃ��B������Î{�݂ƌ����Ȃ���ߔN�}������S��
�@�@�a�ɑΉ�����_�o�Ȃ��炠��܂���B�܂��A430���̃x�b�h�̐�������
�@�@�Ȃ����t�A�Ō�t�s����340�������g���Ȃ�����������܂��B
�@�@�k�a�̈�Ë��_�������ǂ̂悤�ɂ����̂������₵�܂����B
�@����ɑ��āA�ޗnj����a�@��k�a�̋��_�ƂȂ��Ë@�ւɂ�������
�@�@���A�_�o�Ȉ�̈琬���܂ߒ������I�Ɍ�������Ƃ̓��قł����B
����a�ɋꂵ�ݕ��X�ւ̑Ή��Ƃ��āA��a���k�x���Z���^�[��
�@�@����17�N�A�S�R�ی����ɐݒu����܂����B���������������
�@�@���Ƃ̑ΏۂƂȂ銳�҂́A130�ŁA���̓���Ô���������
�@�@���莾�����Ì������Ƃ̑Ώێ�����45�ɉ߂��܂���B
�@�@���̎x���Z���^�[�����Ћˍ��Z�Ւn�Ɉړ]����Ƃ̂��Ƃł������n
�@�@����ʂ̕s�ւȏꏊ�ɂ���A���҂̕��X�̗������l����ƍčl
�@�@����ׂ��Ǝ����܂����B�����ґ��́A���Ћˍ��Z�Ւn�ւ̈ړ]��
�@�@��ʖ���o���A�t���[�̂��ƂȂǂ��l���������������Ƃ��܂����B |

��ʂ��s�ւȏ�ɘV�������ڗ������ޗǕa�@ |
| http://www.ogita-yoshio.com |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
8��7����9��14���ɊJ�Â��ꂽ�ψ���œ��H�����y�яa�ؑ�ɂ��Ď��₵�܂����B
������J�s1300�N�ՊJ�ÂɊ֘A���Ĉ��x�Y���̌������ƕ���{�Ղ����f����s�Ւʂ�̔p�~����荹������Ă���
�@�@���Ƃɂ��Ď���������Ƃ���A���x�Y�����������H�ɂ���K�v���͂Ȃ��Ƃ��܂����B
����a�������̂悤�ɍL�抲�����H�Ƃ��Čv�悳��Ȃ炪�p�r�ύX����������Ă��铹�H�ɂ��āA�W�s�����Ƃ�
�@�@���c�͂���Ă���̂��ɂ��Ď���������Ƃ���A��ʗʂ̌������ȂǍL�抲�����H�̂�������������Ă���A�����
�@�@�W�s�����Ƌc�_����K�v������Ɠ��ق��܂����B
����a�c�I�����͑�a�k���H�̓ޗǃC���^�[�`�F���W�܂ł̃A�N�Z�X�ɂȂ�܂����A���̐����ɂ��Ă͓�Ԑ��̂܂܂�
�@�@���܂����B
������308�������H������ˉ����Ă��a���N����A���˂������ނւ��̂܂ܐi���o���Ȃ����Ԃ́A�����̐�����
�@�@�Ⴄ���̂ł��肻�̗��R�ɂ��Ď����ƁA���H��ʖ@�ߏ�͉\�Ȃ��̂́A���l����ł̎��̕p�����Q�l�ɂ����[�u��
�@�@�����A�O���ƈႤ�Ή��ɂ��Ĕ��Ȃ��A���㌟���������Ƃ��܂����B |

